今回は、建築学生におすすめの本・参考書をジャンル別に紹介します。
建築初学者向け
こちらは、建築系の学校に入学する前後や、建築初学者におすすめの本・参考書になります。
ようこそ建築学科へ
発売日:2014年3月25日 ページ数:216P
「ようこそ建築学科へ」は、これから建築を学ぶ学生や、進路選びに迷う人に向けたガイドブックになります。
大学や高専、専門学校など多様な建築系教育の違いから、授業や課題の取り組み方から日常の過ごし方、学外での体験、将来の進路までをカバーしています。
建築学科のリアルな学生生活が、楽しさと苦労の両面から紹介され、建築の奥深さに自然と引き込まれる内容になっています。
日々をどう過ごすか、実践的なアドバイスが詰まった一冊で、これから建築を学ぶ人におすすめです。
建築を楽しむ教科書
発売日:2022年9月12日 ページ数:192P
「建築を楽しむ教科書」は、BRUTUS誌の建築特集3冊をまとめた一冊です。
第1部では、日本を代表する24人の建築家を紹介し、彼らの作品や考え方を通して現代建築の魅力を知ることができます。
第2部は、伝統建築に焦点を当て、日本の歴史や文化を映し出す建築の美しさとその背景を丁寧に解説しています。
第3部では、小規模ながらも個性豊かで人々に愛される建築を特集し、身近な視点から建築の楽しさを伝えています。
建築の幅広い魅力を、写真や文章でじっくり堪能できる編集で、これから建築を学習する人におすすめの一冊です。
建築をめざして
発売日:1967年12月5日 ページ数:216P
「建築をめざして」は、近代建築の父と称されるル・コルビュジエによる重要な一冊です。
本書は、都市や建築における新しい時代の到来を告げる宣言であり、ル・コルビュジエが伝統的な慣習に縛られながらも革新を模索した姿勢が鮮明に表れています。
内容は、建築の基本的な要素から、工学技師としての美学、都市計画の教訓や建築革命への問題提起まで幅広く、都市や建築を学ぶ人々にとって刺激的な内容となっています。
ル・コルビュジエ自身の豊富な経験と思想が凝縮されたこの一冊は、近代建築の核心に迫り、建築の本質や未来を考えるうえで欠かせない名著であり、建築を志す人全員におすすめの本になります。
建築家になりたい君へ (14歳の世渡り術)
発売日:2021年2月26日 ページ数:228P
「建築家になりたい君へ(14歳の世渡り術)」は、建築家・隈研吾氏が10代の若者に向けて、自身の人生と建築への思いを語る一冊です。
建築を志したきっかけ、悩み、失敗、世界での経験など、リアルで等身大の言葉がつづられています。
10歳で建築家を目指した隈氏が、動物好きだった少年時代から、アフリカへの夢、アメリカ留学での気づき、初めての建築、予算ゼロの挑戦、中国の田舎でのプロジェクト、そして国立競技場に至るまで、まるで小説のように彼の歩みを追体験できます。
「建築家とは待てる人」「小さな仕事をやり続ける」「恥をかくことは挑戦の第一歩」など、若者の背中をそっと押す、やさしく力強いメッセージの数々に加え、建築の話にとどまらず、「人を信じること」「大人との向き合い方」「社会との接点」など、広く人生について学べる内容となっています。
建築に興味がある人はもちろん、将来に悩むすべての若者にもおすすめの一冊になります。
教養としての建築入門-見方、作り方、活かし方
発売日:2023年7月20日 ページ数:256P
「教養としての建築入門-見方、作り方、活かし方」は、建築に詳しくない人でも楽しめる、建築の魅力を広く深く伝える入門書です。
美術館や旅館など、私たちが日常でふと感動する建築を、「機能」と「美」の両面から紐解きながら、日本と西洋の建築史を知ることができる構成になっています。
また、建築を「観賞」「設計」「社会」という3つの視点から解説し、過去から現代に至るまでの建築の進化と、そこに込められた思想を丁寧に紹介しています。
さらに、著名建築家たちの仕事にも触れ、建築を見る楽しみが一層深まります。
観光や街歩きの際に、建築の背景を知るだけで体験が何倍にも広がる「教養」としての建築の楽しみ方を教えてくれる一冊です。
建築に興味を持ち始めた人や、建築をより楽しみながら学習したい人におすすめです。
眠れなくなるほど面白い 図解 建築の話: 身近な建物が楽しくなる ナゾとギモンを一挙解決!
発売日:2020年3月25日 ページ数:128P
「眠れなくなるほど面白い 図解 建築の話」は、身近な建物の謎や疑問を楽しく解き明かす一冊です。
日本の古民家や寺社、城、庭から近現代の建築まで、建築家ならではの視点で建物の見方や楽しみ方を豊富な図解でわかりやすく解説しています。
たとえば、「屋根の形はどう決まるのか」「看板建築の構造」「うだつの意味」など、暮らしに根ざした日本建築の魅力や文化を気軽に学べます。
本書は、耐震・免震・制震工法の違いなど、実生活に役立つ知識も含み、理系の知識がなくても理解できる内容となっております。
また、5つのパートに分かれており、「日本建築の知られざる秘密」や「寺社のこだわり」「城と庭の美意識」「建築を支える技術」など多角的に建築の奥深い世界を紹介しています。
文章と図解が対になった見やすい構成で、さっと読み進められながら専門的な知識も身につくため、建築初心者におすすめです。
会社を辞めて建築家になった
発売日:2023年3月31日 ページ数:208P
「会社を辞めて建築家になった」は、建築を志す人や独立を考える若手設計者に向けた、実践的かつリアルな一冊です。
著者は現代建築の第一線で活躍する建築家・坂牛卓氏で、日本を代表する大手設計事務所「日建設計」を経て、独立して建築家としての道を切り拓いてきた人物です。
本書では、組織設計事務所から個人で活動する「建築家」になるまでの経緯と、その裏にある悩みや決断、現実的な課題を赤裸々に語っています。
独立のタイミング、仕事の獲得、建築家としての哲学など、華やかに見える道の裏側にあるリアルな声が詰まっており、建築学生にとっても現実を知りながら前に進むための心強い道しるべとなる一冊です。
建築思想・哲学
こちらは、建築家・建築に携わる人々・建築が出来上がる過程の背景にある思想や哲学について知りたい人におすすめの本・参考書になります。
建築思想図鑑
発売日:2023年9月23日 ページ数:256P
「建築思想図鑑」は、建築の歴史と理論を学ぶ上で押さえておきたい63のキーワードを、豊富なビジュアルと第一線の研究者による明快な解説でひも解く、画期的なガイドブックです。
時代は近代以前から現代までを網羅し、それぞれの思想が、建築の本質に迫る視点から丁寧に紹介されており、専門用語や複雑な概念も、視覚的にすっと理解できるよう工夫されています。
そのため、建築を学び始めたばかりの人から実務に携わるプロフェッショナルまで、幅広い層から高い支持を得ています。
また、思想同士のつながりや時代背景が見渡せる構成になっており、建築を「つくる」人にも「語る」人にも、自分の考えに深みと説得力を与える基盤を築いてくれる一冊です。
建築を体系的に学び、思想の広がりを知りたいすべての人に、いまこそおすすめしたい決定版の入門書です。
建築家という生き方
発売日:2001年8月3日 ページ数:406P
「建築家という生き方」は、建築総合誌「日経アーキテクチュア」が1976年の創刊以来行ってきた数多くのインタビューから、選りすぐりの27人の建築家・構造家・職人たちの言葉を収録した一冊です。
村野藤吾から安藤忠雄、原広司、磯崎新、黒川紀章、伊東豊雄、槇文彦まで、世代を超えた多様な建築家たちが、自らの思想、作品、そして人生観を語ります。
さらに、構造家や宮大工、瓦師といった人々の声も加わり、建築を取り巻くリアルな現場の姿が立体的に描かれています。
収録されたインタビューは、掲載年代にとらわれず5部構成で再編集されており、それぞれの建築家が語る言葉は、建築を志す人だけでなく「働くとは何か」「創造するとは何か」を考えるすべての人の心に響きます。
建築を牽引した者たちの葛藤、変化、信念を知ることができる1冊となっています。
建築家の基点 「1本の線」から「映画」まで、13人に聞く建築のはじまり
発売日:2022年5月6日 ページ数:304P
「建築家の基点 「1本の線」から「映画」まで、13人に聞く建築のはじまり」は、現代を代表する13人の建築家に、「建築の原点=基点」についてインタビューした、読み応えのある対話集です。
本書は、「物・間・関係性・世界」という4つの切り口で構成され、建築の創造における出発点を、各建築家の作品や思想を通して浮かび上がらせていきます。
それぞれが、まったく異なる起点から建築を思考し、アプローチしていますが、共通しているのは、「建築とは何か?」という根本的な問いに対して、明確な哲学をもって向き合っています。
単なる作品解説ではなく、創造の背景や原風景、思想のルーツにまで深く迫る本書は、建築に携わるすべての人にとって、思考を刺激する貴重な一冊です。
建築を学びはじめた学生から、長年実務に携わるプロまで、幅広い層におすすめできる内容です。
連戦連敗
発売日:2001年9月3日 ページ数:232P
「連戦連敗」は、世界の設計コンペで敗北を重ねながらも、そこから多くを学び成長してきた安藤忠雄の東京大学大学院での講義録です。
この本のテーマでは、建築を「闘い」と捉え、逆境のなかで創造が生まれることを説いています。
保存と再生の都市・建築論、環境問題との向き合い方、そして過去を超える挑戦など、多岐にわたるテーマを扱い、建築家のリアルな挑戦と深い洞察が詰まった、貴重な建築論集となっています。
誰のために 何のために 建築をつくるのか
発売日:2025年4月17日 ページ数:176P
「誰のために 何のために 建築をつくるのか」は、世界的建築家・伊東豊雄が自身の代表作を振り返りながら、現代建築の本質と未来について自由に思索する最新エッセイ集です。
大阪・関西万博の「EXPOホール」や「おにクル」など話題作なども例として紹介しています。
第1章では、建築の意味や現代建築の特徴を探り、機能にとらわれない「場所づくり」を論じます。
第2章は自然と調和した建築の具体例を、多数の作品を通して解説しています。
第3章では、人に感動や生きる力を与える建築の可能性や建築家の使命について考察しています。
図版・写真も豊富で、建築の哲学と実践を深く知ることができる一冊です。
負ける建築
発売日:2019年11月16日 ページ数:278P
「負ける建築」は、世界的建築家の隈研吾が、環境に対して屹立する「勝つ建築」から、外力を受け入れる「負ける建築」へと、これからの建築のあり方を問い直した建築論集です。
かつて建築は、都市の中で目立ち、権力を象徴することが求められてきましたが、21世紀の今、そのあり方は限界に直面していると本書では述べられています。
本書では、20世紀の建築史や思想、アートを横断しながら、「透明性」「デモクラシー」「ヴァーチャリティー」などのキーワードを軸に、新しい建築の方向性を模索していきます。
新国立競技場の設計に携わった著者だからこそ語れる、環境や人々と“共にある”建築とは何か、「強い建築」だけが優れているわけではないという、新しい視点が得られるはずです。
静かに時代へと対峙する建築の思想に触れてみたい方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。
紙の建築 行動する――建築家は社会のために何ができるか
発売日:2016年6月17日 ページ数:240P
本書は、阪神・淡路大震災をきっかけに、紙管を構造材として仮設住宅やシェルターに応用した建築家・坂茂が、世界各地の被災地や難民キャンプで実践してきた「紙の建築」の歩みと、その背後にある思想を、自らの言葉で振り返ったドキュメントです。
仮設住宅「紙のログハウス」、ルワンダ難民への支援、日本館(ハノーバー万博)など、人道支援と建築デザインを結びつける数々のプロジェクト、ボランティアとの連携、国連との協働、現場での葛藤、建築家としての使命を問い直すリアルな記録と哲学が詰まっています。
「人は建物で命を落とすが、建築家は命を守ることもできる」というテーマから、社会に開かれた建築のあり方を模索する、すべての建築関係者に読んでほしい一冊です。
建築について話してみよう
発売日:2007年9月1日 ページ数:220P
本書は、今注目を集める建築家・西沢 立衛による単行本です。
対話形式のインタビューや具体的なプロジェクト解説を通じて、建築が都市や自然、社会とどのように関わり合うのかを深く考察しています。
そして、建築を取り巻く環境や歴史、素材の使い方、空間の連続性など、多角的な視点から建築の未来像に迫ります。
建築に興味のある方はもちろん、創造的な空間づくりに関心があるすべての人にとって、刺激的な一冊です。
建築の七燈
発売日:1997年9月1日 ページ数:334P
「建築の七燈」は、ジョン・ラスキンによる建築とは何かという本質に迫る思想書です。
19世紀イギリスの美術評論家であったラスキンが、建築における美と精神性を7つの「灯(ともしび)」になぞらえて説いた本書は、単なる技術書やデザイン論とは一線を画す、建築哲学の原点ともいえる作品です。
「犠牲」「真実」「力」「美」「生命」「記憶」「服従」という7つの価値観を軸に、建築がいかにして人間の信仰や文化、自然との調和を体現すべきかを語る内容は、現代においても多くの示唆を与えてくれます。
特に、素材や構造の誠実さ、自然から学ぶ美しさといった視点は、持続可能な建築が求められる今の時代にも通じる考えです。
建築学習者やデザイナーに限らず、美や文化に関心のある人にとっても、おすすめの一冊です。
藤本壮介 建築への思索 世界の多様さに耳を澄ます
発売日:2019年5月23日 ページ数:84P
「藤本壮介 建築への思索 世界の多様さに耳を澄ます」は、現代建築を牽引する建築家・藤本壮介の思考の原点を紐解く、貴重な一冊です。
建築を志したきっかけから、大学時代、事務所設立初期の模索の日々、そして代表作に込められた背景や施主との関係性に至るまで藤本自身の言葉で語られ、建築とは何か、そしてその先にある未来への思索を深めていきます。
世界の多様さに耳を澄ましながら、自然や人間の営みに寄り添うような建築を目指す藤本の姿勢が、静かで力強い言葉で語られており、読者に深い余韻を残します。
建築を学ぶ人にも、創作に向き合う人にも、思考の広がりを与えてくれる一冊です。
美術館をめぐる対話
発売日:2010年10月15日 ページ数:224P
「美術館をめぐる対話」は、建築家・西沢立衛が、建築・アート・都市・公共空間の境界を超えて活躍する人物たちと交わした対話を通じて、「美術館」という空間とその建築的・社会的意味を深く掘り下げる一冊です。
金沢21世紀美術館、ルーヴル・ランス、十和田市現代美術館など、国内外で注目を集めた美術館設計の経験をもとに、美術館が「開かれた公共空間」としていかに都市や人々と関係を結ぶべきかが語られます。
単なる建築論ではなく、都市計画・哲学・芸術論も交差する知的対話の連続は、美術館という場所の可能性を問い直す機会となるでしょう。
建築・美術・都市に関心のある読者はもちろん、これからの「公共空間」のあり方にヒントを求めるすべての人におすすめできる一冊です。
建築理論
こちらは、建築をどのように考えていくかの理論を知りたい人におすすめの本・参考書になります。
原っぱと遊園地
発売日:2004年10月1日 ページ数:237P
発売日:2008年4月1日 ページ数:235P
「原っぱと遊園地」は、建築家・青木淳による建築論集です。
本書では、あらかじめ用途が決まっている「遊園地」のような建築と、そこでの行為によって意味が形作られていく「原っぱ」のような建築という対比を通じて、「その場の質」が建築においてどう成立するのかを探ります。
潟博物館やルイ・ヴィトン表参道、青森県立美術館、さらには住宅作品など、多様なプロジェクトを題材に、青木が建築における空間、時間、利用者の関係性を自筆スケッチや写真とともに深く考察しています。
動線や場所の成り立ち、既存建築の意味、阪神大震災の教訓、さらには建築の「アクチュアリティ」や「ウイルス的設計論」など、多岐にわたるテーマを展開しています。
建築の根源的な問いに迫る、思想的で深みのある論考集として、建築の場の在り方について関心のある方に強くおすすめします。
空間〈機能から様相へ〉
発売日:2007年12月14日 ページ数:380P
「空間〈機能から様相へ〉」は、建築家・原広司による哲学的な建築論です。
20世紀まで支配的だった「機能的で均質な空間」という考えに対し、空間の「様相」といった表情や雰囲気、見え方といった多様な状態を重視する新しい視点を提示します。
著者は建築学や哲学、現象学、仏教学など幅広い知識と、世界各地の集落調査の成果を基に、日本の伝統的住居の曖昧で多層的な境界の特徴を分析しています。
こうした考察を通じて、境界のあいまいさも空間の大切な様相であると説き、21世紀の建築設計に求められる新たな空間理解を示しています。
建築の機能について考えたい人におすすめの一冊になります。
空間へ
発売日:2017年10月5日 ページ数:578P
「空間へ」は、建築家であり理論家でもある磯崎新の思考の原点を収めた著作集です。
1960年代に執筆された約30篇の論文・エッセイを時系列に収録し、若き日の磯崎がいかにして建築を思考し、現代都市と向き合っていたかを描き出します。
本書は単なる建築論ではなく、都市や空間、記号、記憶といった広範なテーマを内包し、哲学的かつ詩的な眼差しで世界を捉えようとする試みでもあります。
「未完成」や「廃墟」といった象徴的なイメージを通して、建築を文化や歴史、幻想の中に位置づける姿勢は、今なお新鮮で鋭く、読み手に深い思索を促します。
日本や海外の都市を巡る観察や分析には、空間に潜む無数の意味や重層的な価値への洞察があふれ、建築を超えて芸術や思想の領域にまで踏み込む姿勢が感じられます。
本書は、私たちが生きる都市や環境がいかにして人の妄想やロマンの集積によって形づくられているかを静かに語りかける一冊になっています。
建築を語る
発売日:1999年6月1日 ページ数:259P
「建築を語る」は、独学で建築を学び、世界的建築家となった安藤 忠雄が、東京大学大学院での講義をもとにまとめた貴重な建築論であり、人生論でもあります。
戦後の激動期を生き、建築に夢を見てきた著者は、自身の原点である「住吉の長屋」から「淡路夢舞台」までの創作過程を通じて、建築を構想し実現する喜びと困難、そして社会的制約と自由のせめぎ合いを率直に語ります。
建築とは何かを深く掘り下げる本書には、時代の流れの中で建築家が果たす役割や、創造の本質に迫ろうとする強い意志が貫かれており、未来を志す読者に対する熱いメッセージが込められています。
建築の「考える自由」を第一とする著者の姿勢は、社会の変化や制約の中にあっても、自らの想像力で現実を動かそうとする建築家の在り方を鮮やかに描き出した一冊になります。
建築家なしの建築
発売日:1984年1月25日 ページ数:172P
「建築家なしの建築」は、系図なしの建築、つまり無名の人々による風土に根ざした建築のヴァナキュラー建築を、世界各地から集めた図版で紹介しています。
本書は一種の知的な建築旅行案内でもあり、現代の都市や建築が忘れかけている「生活に根ざした創造性」や「自然と共生する知恵」が、ページをめくるごとに現れ、読む者に強い示唆を与えます。
テーマとしては、「死者の家」「穴居生活」「遊牧民の建築」「草の構造体」など、建築の常識をくつがえすような内容が並んでいます。
あるのは、気候や地形、素材といった条件を巧みに読み取った「暮らしのための建築」の姿です。
本書は、近代建築の枠組みに疑問を持つ人、持続可能な建築に関心がある人、あるいは「建築とは何か」を根本から見つめ直したい人にとって、思想的にも視覚的にも深く訴えかけてくる1冊です。
設計手法・コンセプト
こちらは、建築設計をする際に役立つ具体的な情報を知りたい人におすすめの本・参考書になります。
代謝建築論: か・かた・かたち
発売日:2008年3月1日 ページ数:233P
「代謝建築論: か・かた・かたち」は、建築設計の本質を深く掘り下げた菊竹清訓による名著の復刻版です。
本書では、「か」(本質論的段階)、「かた」(実体論的段階)、「かたち」(現象論的段階)という三つの視点から建築デザインの方法論を提示しています。
内容は、デザインの方法論や伝統、見えるものと見えないものの秩序、そして建築が環境の中で代謝し続ける装置であるという考え方を展開しています。
さらに建築家の思想にも触れ、設計という行為の意味と役割を多角的に考察しています。
建築が社会的インフラとして果たす役割や、その変化し続ける性質を理解したい建築家や学生にとって、おすすめの一冊です。
点・線・面
発売日:2020年2月9日 ページ数:224P
「点・線・面」は、国立競技場をはじめ、自然素材を駆使した建築で世界を魅了する建築家・隈研吾が、「点」「線」「面」という3つの視点から建築を捉え直す書き下ろしのエッセイとなっています。
建築はもっと軽やかに、風通しよく、人や自然と調和できるはずという考えから、トビゲラの巣作りに着想を得た「点」の建築、繊細な技術と伝統を継承する「線」、布のように包みこむ「面」という素材や構法の解釈を通じて、建築と人、環境との関係を再構築する思索の旅が展開されます。
図版・写真は200点以上収録されており、コンピュテーショナルデザインや新しい物理学にも触れながら、現代建築の可能性を読み解く、知的刺激に満ちた内容です。
建築を素材や、「点」「線」「面」のように抽象化して考えたい人におすすめです。
建築スタディ 発想の方法: デザインを決めた50人の模型・ドローイング
発売日:2024年6月22日 ページ数:224P
「建築スタディ 発想の方法: デザインを決めた50人の模型・ドローイング」は、建築のデザインはどのタイミングで、どのように決まるのかという題材から、50人の著名建築家が辿った発想の過程を、模型やドローイングの「試行錯誤の瞬間」と「決定の瞬間」を見比べながら明らかにする一冊です。
「方法」「関係」「構造」「空間」「表皮」「ディテール」「社会」「環境」といった多様なテーマに沿い、それぞれの章で具体的なプロジェクトとともに発想のヒントが紹介されているため、設計の裏側に隠された思考や創造のプロセスがリアルに理解できます。
青木淳、中山英之、隈研吾、伊東豊雄、千葉学、長谷川逸子ら第一線の建築家たちが、いかにして発想を得てきたのかという思考の瞬間を追体験できる内容は、建築学生や設計者はもちろん、建築に興味を持つすべての人に貴重な示唆を与えます。
建築設計のアイデア過程で悩んでいる人にもすすめの一冊になっています。
西沢立衛|西沢立衛建築設計事務所スタディ集
発売日:2025年2月27日 ページ数:112P
「西沢立衛|西沢立衛建築設計事務所スタディ集」は、20世紀のモダニズムやポストモダニズムとは異なる建築思想を模索する若手建築家たちに焦点を当てたシリーズの第4弾として、本書は建築家・西沢立衛の創作過程に迫ります。
手描きスケッチ、図面、模型、メモ、フォトコラージュなど多様な表現を通して、西沢の思考の断片とスタディの積み重ねが生々しく記録されており、「森山邸」「ガーデンアンドハウス」「HOUSE A」など最新プロジェクト11件を紹介しています。
建築とは固定された答えではなく、試行錯誤の連続であり、スタディを重ねることが創造の自由そのものであることが、本書を通じて力強く伝わってきます。
2009年刊の名著を重版復刊した一冊であり、建築に向き合うすべての人に刺激を与える貴重な記録です。
建築設計の具体的な過程の例を知りたい人におすすめの一冊になります。
住宅読本
発売日:2004年6月23日 ページ数:128P
「住宅読本」は、良い住宅とは何かを、建築家が暮らしの視点から深く考え抜いた一冊です。
本書は手ざわり、台所、家具、あかりなど、心地よい住まいに必要な12の条件を、約70点のカラー写真やイラストで丁寧に解説しています。
自然素材や高断熱などの性能面に注目が集まる昨今ですが、本書は「形」や「機能」だけでなく、「暮らしの内側」から住宅を見つめる視点を教えてくれます。
写真やイラストの豊富さも魅力で、読者は言葉だけでは伝わりにくい住宅の質感や空間の空気感を感じ取れるでしょう。
住宅設計の第一人者がまとめた“心地よい住まい”のための十二の条件は、住宅を単なる住む場所ではなく、「暮らしを育む場」として見直したい方にとって、必読のガイドブックです。
より良い住宅の在り方について知りたい人におすすめです。
小さな森の家: 軽井沢山荘物語
発売日:1996年4月1日 ページ数:111P
「小さな森の家: 軽井沢山荘物語」は、日本を代表する建築家・吉村順三が自ら案内する軽井沢の名作山荘を紹介した一冊です。
建築家自身の視点で、外観から室内空間まで丁寧に解説しており、心地よい空間づくりの工夫や四季と調和するデザインの魅力を深く味わえます。
本書では、吉村が最初に描いた山荘の図面原図も初めて公開されているほか、平面図や断面図、各部の詳細図も掲載しています。
四季折々の美しい写真とともに、小さなプランに秘められた居心地の仕掛けや設備への細やかな配慮も読み解けます。
軽井沢での暮らしの情景とともに、建築家の思想が凝縮されたこの山荘の魅力を、実際の設計図面や写真で感じられる、建築ファン必携の一冊です。
隈研吾 オノマトペ 建築 接地性
発売日:2024年8月2日 ページ数:256P
「隈研吾 オノマトペ 建築 接地性」は、建築と大地、人と空間とのつながりを、オノマトペ(擬音語・擬態語)を通じて探る一冊です。
建築家・隈研吾が提案するのは、モダンやポストモダンを超えた、身体感覚や自然との結びつきを重視する建築です。
建物を「接地」させるための新たな視点として、13のオノマトペ(ぱらぱら、ぐるぐる、つんつん など)を設計に取り入れ、自身の56の作品を分類・解説します。
オノマトペは単なる表現ではなく、素材の質感や構造、空間の関係性を示す設計の道具として語られています。
国立競技場、V&A Dundee、浅草文化観光センター、高輪ゲートウェイ駅など代表作も多数掲載され、図版も豊富です。
隈建築の「やわらかい思想」に触れられる、視覚と感性に響く建築論です。
感覚的で表しにくいことを建築に取り入れたい人におすすめの一冊になります。
人間と建築: デザインおぼえがき
発売日:2011年11月11日 ページ数:292P
「人間と建築: デザインおぼえがき」は、1970年に刊行された丹下健三の著作の復刻版で、雑誌などで発表された文章をまとめています。
内容は日本建築家の役割や民衆と建築との関係性、現実と創造の対比、人と近代技術の関係性、機能と空間のつながりなど多岐にわたります。
丹下健三の人間と建築の関係性を知ることができる重要な一冊となっています。
建築と人との関係について考えたい人におすすめの一冊になります。
藤本壮介―原初的な未来の建築
発売日:2014年6月1日 ページ数:143P
「藤本壮介―原初的な未来の建築」は、建築家の藤本壮介とは何者か?から始まる作品集です。
彼は「建築とは何か」「住むとは何か」という根源的な問いを起点に、幾何学的や原初的な未来の建築、人口と自然の建築といったテーマを展開していきます。
新しい未来の建築の可能性を探る貴重な一冊です。
建築環境デザインのディテール 光・熱・風・水・音
発売日:2024年12月3日 ページ数:160P
「建築環境デザインのディテール 光・熱・風・水・音」は、近年の気候変動を踏まえ、建築と環境の一体的なデザイン手法をビジュアル豊かに解説する一冊です。
光・熱・風・水・音という自然要素をいかに建築に取り入れるかのポイントを示し、設計の6ステップ(気候の理解から環境性能の設定まで)を体系的に紹介しています。
さらに、環境配慮を実践する18の優れた建築事例を詳細なディテール図と共に収録しています。
著名な建築家や設計事務所による多彩なプロジェクトから、環境と調和したデザインの具体例を学べます。
環境と建築の深い関係を理解し、設計に活かしたい人におすすめの一冊です。
建具の手がかり: 境界を操作する39の手法
発売日:2024年9月22日 ページ数:188P
「建具の手がかり: 境界を操作する39の手法」は、建具を通じて空間の「境界」を自在に操る39の建築事例を、建築家の藤田雄介が詳しく解説する一冊です。
建具が空間を仕切りつつもつなぐ役割を果たすこと、その多様な可能性を豊富な図面や写真とともに示し、建築の境界の操作や空間の質を深く考察。感染症や生産、衣服や工芸との関連などコラムも収録し、建具を中心に建築の新たな理解を促します。
「距離」「構え」「環境」「ディテール」「再利用」の章構成で、スカイハウスや旧前川邸、聴竹居、吉村順三の住宅など多彩な作品を扱い、建具の多様な機能と表現を網羅しています。
細かい詳細な部分からも建築を考えたい人におすすめの一冊です。
建築断面 矩計図集
発売日:2025年2月10日 ページ数:160P
「建築断面 矩計図集」は、建築の垂直断面を表す矩計図に焦点をあてた図集で、16組の建築家による重要なプロジェクトの矩計図と解説を収めています。
本書では、著名な建築家たちが矩計図の意味や役割をさまざまな視点から論じ、矩計図が形やふるまいを読み解く手引きであり、建築に命を吹き込む重要な表現手段であることを伝えています。
収録されている作品は歴史的文化施設から住宅、公共施設まで多彩で、これから建築を志す人にとって貴重な資料となる内容です。
図面からも建築を学びたい人におすすめの一冊になります。
プロジェクト図解 地域の場を設計して、運営する: 設計事務所15の実践
発売日:2025年3月5日 ページ数:192P
「プロジェクト図解 地域の場を設計して、運営する」は、建築家が地域に根ざした空間を設計し、自ら運営も手がける15の実践事例を紹介した一冊です。
カフェや社食堂、銭湯、図書館、宿泊施設など、建築が地域の暮らしにどのように関わり、育まれていくかを、図面や写真、収支表、ネットワーク図といった豊富な資料で分かりやすく理解できます。
本書では、プロジェクトを「投資」「持続」「多拠点化」の3つのフェーズに分類し、それぞれの成長段階や経営の工夫、地域との関係性を丁寧に読み解きます。
設計にとどまらず、運営や経済性まで見据えた視点が貫かれており、建築が「道具」としてまちにどう機能するかをリアルに伝える内容です。
建築や地域づくりに関心のある人はもちろん、これから空間運営を考える人にとっても、おすすめの一冊になります。
小さな家
発売日:1980年1月1日 ページ数:85P
「小さな家」は、ル・コルビュジエが自身の両親のためにレマン湖畔に設計した、わずか60㎡の小住宅をめぐる記録であり、彼の建築思想の原点を知るうえで極めて貴重な一冊です。
自然に任せた屋上庭園の描写には、空間の余白や自然との共生を尊重するコルビュジエの姿勢がにじみ出ています。
本書は写真やスケッチがふんだんに使われており、建築の専門知識がなくても楽しめる構成です。
家づくりに込められた愛情、家族への配慮、慎ましやかな美意識といった人間的な側面が随所に表れており、モダニズム建築の巨匠の、あたたかく繊細な一面を垣間見ることができます。
建築入門者にも、建築の本質に触れたい人にも強くおすすめできる一冊になります。
都市
こちらは、建築だけでなく、建築を取り巻く都市について学びたい人におすすめの本・参考書になります。
基礎から応用までしっかりわかる 都市計画法の教科書
発売日:2025年5月11日 ページ数:264P
「基礎から応用までしっかりわかる 都市計画法の教科書」は、都市計画に関わる人すべてにとって基礎知識をしっかりと身につけられる一冊です。
都市計画法の全体像を体系的に解説しつつ、それを補完する多くの個別法との関係まで丁寧に説明しており、法の構造と運用実態の両方が理解できる構成になっています。
本書は、「都市計画法とは何か?」という根本的な問いから始まり、その目的や成り立ち、都市計画の種類とその意義、計画を実現するための具体的な手段までを、段階的に学べるように設計されています。
また、都市マスタープランや用途地域、風致地区、地区計画といった専門的な内容にも触れながら、実際にどのように都市計画が進められ、運用されているかを具体的にイメージできるよう導いてくれます。
各章では冒頭に要点が「Point」として示され、最後には復習問題が用意されているため、理解の定着にも配慮された親切な構成です。
応用・理論編では、住民の意見の反映、都市計画をめぐる現代的課題や理論的な争点にも踏み込み、実務だけでなく思考の幅を広げたい読者にも応える内容となっています。
都市計画の初学者はもちろん、実務に関わる建築関係者にとっても、法の正確な理解と実務とのつながりを整理する上で役立つ、実践的かつ理論的な内容になります。
都市計画を体系的に学びたい人におすすめの一冊になります。
輝く都市
発売日:1968年12月5日 ページ数:280P
「輝く都市」は、ル・コルビュジエによる20世紀都市計画の象徴的な構想であり、都市計画の考え方に大きな影響を与え続けてきた名著です。
本書ではその都市計画の観点が詳しく述べられ、都市のあり方や未来の社会構造を考えるうえで重要な考えを提供しています。
内容は、技術的・精神的側面の統合や新しい機械主義社会の構築、従来の都市観念の刷新、具体的な都市計画の原則や実践に至るまで、多角的に展開しています。
特に都市の存在意義について関心を持つ人にとっては必読の一冊です。
新訳 明日の田園都市
発売日:2016年10月6日 ページ数:292P
「新訳 明日の田園都市」は、近代都市計画の創始者エベネザー・ハワードによる、住民の視点から考えられた初の都市計画論の名著を新たに訳し直した一冊です。
本書の主な内容は都市の物理的な形態よりも社会システムや財政面に重きを置いています。
ハワード自身が描いた理想は、最新技術を取り入れた革新的なハイテク都市の姿でもあり、単なる自然豊かな郊外とは一線を画しています。
本書は、田園都市の収益や歳出の仕組み、行政管理、自治体支援、禁酒法改革など多角的な社会制度の提案から、ロンドンの未来像に至るまで幅広く扱い、実際にレッチワースやウェリンに着工した実践例も踏まえています。
都市計画や社会設計を学ぶ人にとって、現代のニュータウンやスマートシティのルーツを理解する上で欠かせない重要な本です。
都市を社会の観点からも考えたい人におすすめの一冊になります。
建築と都市: デザインおぼえがき
発売日:2011年11月1日 ページ数:188P
「建築と都市: デザインおぼえがき」は、主に1960年代に書かれた都市に関する論考をまとめた一冊です。
1964年の東京オリンピックや1970年の大阪万博といった国家的イベントに関わった著者は、この時期に政府の首都圏整備計画に対抗する「東京計画1960」や、日本列島の未来像を描いた「東海道メガロポリス」を提案しました。
本書は、著者が目指した日本の都市環境の構想と、1960年代に輝いていた世界的な都市デザインの思想を伝えています。
現代都市に人間性豊かな空間秩序を取り戻す視点も特徴です。
建築と都市の関係性について考えたい人におすすめの一冊になります。
都市のイメージ 新装版
発売日:2007年5月29日 ページ数:286P
「都市のイメージ」は、都市に生きる人々の視覚や心理、行動様式に着目し、「イメージアビリティ」という独自の概念を提示した、都市デザインにおける名著です。
著者ケヴィン・リンチは、本書を通して、人々が都市をどのように認識し、記憶し、経験するのかという視点から、美しく、楽しく、そして喜びに満ちた都市とは何かを探ります。
ボストン、ジャージー・シティ、ロサンゼルスの3都市を事例に、都市の「パス(道)」「エッジ(境界)」「ディストリクト(地区)」「ノード(結節点)」「ランドマーク(目印)」という5つの構成要素を軸に分析を行い、都市の形態やその印象がどのように形成されるのかを具体的に示しています。
都市に関心のあるすべての人にとって必読の一冊であり、再刊された本書は、今あらためて「都市とは何か」を見つめ直すための格好の手引きとなる一冊になります。
見えがくれする都市
発売日:1980年6月20日 ページ数:234P
「見えがくれする都市」は、槇文彦の「奥の思想」を中心に据え、江戸から現代の東京へと続く都市の形成過程を多角的に考察した刺激的な都市計画論です。
複雑な地形や自然条件の中で江戸の町がどのように形づくられ、その痕跡が今の東京にどのように潜在しているのかを、槇文彦自身の視点に加えて高谷時彦、若月幸敏、大野秀敏といった専門家の分析を交えながら示唆豊かに解き明かしています。
都市の道の構図や微細な地形の意味、まちの表層的な特徴まで、様々な角度から都市の「見えがくれ」する多層的な姿を読み解くことで、都市を深く理解し、デザインする上での新たな視座を提供する内容となっています。
東京の都市がどのように形成されたかを知りたい人におすすめの一冊になります。
ランドスケープ
こちらは、ランドスケープや庭、外構の設計について学びたい人におすすめの本・参考書になります。
風景をつむぐディテール: 土地・場所・時の設計図集
発売日:2024年12月1日 ページ数:160P
「風景をつむぐディテール:土地・場所・時の設計図集」は、ランドスケープデザインの図面を一まとめた一冊です。
51作品の詳細な設計図を通じて、その場所固有の風景や環境を活かす「ローカリティ」、素材の表情や生き物との共生による「多様性」、環境とつながり持続可能性を重視する「サステナビリティ」、変化に柔軟に対応し地域に溶け込む「しなやかさ」、そして歴史や物語を映し出す「ナラティブ」の5つのテーマで構成されています。
各章では具体的なプロジェクトを例に、周囲の風景を取り込む工夫や緑や水環境の重層的なデザイン、自然環境を尊重した環境基盤の整備、雨水利用や防災施設のしなやかな設え、そして歴史的記憶を継承する石積みや庭園など、土地と時間をつむぐ多様な視点と技術が豊富に紹介されています。
これにより、ランドスケープが単なる装飾や空間づくりに留まらず、地域の環境や文化と深く結びついた「生きた風景」を創造する設計の思想が明らかにされており、持続可能な環境づくりに取り組む設計者や学生にとって貴重な参考資料となっています。
地域や街をつなぐランドスケープを考えたい人におすすめの一冊になります。
建築と造園をつなぐ ランドスケープデザイン入門
発売日:2025年1月10日 ページ数:156P
「建築と造園をつなぐ ランドスケープデザイン入門」は、敷地の余白から住宅や公共施設の屋外空間まで、緑豊かな空間を設計・計画するためのランドスケープデザインの基礎知識を網羅した入門書です。
全14のレッスンには各章の冒頭にはディスカッション課題、章末には住宅の庭や公共広場、歩道などの演習問題とその解説が掲載されており、実践的に学べる構成です。
内容はデザインの基本から敷地分析、図面の描き方、植栽計画や外構の素材選び、遊具や休憩施設の設置、高低差をつなぐ造成や階段、視線や環境の調整、防犯・防災、伝統的庭園から近現代の公園デザイン、歴史的景観や賑わいづくり、さらには海外のランドスケープアーキテクチャーの動向と日本での可能性まで、多角的にランドスケープデザインの全体像を学べます。
建築士製図試験の外構対策としても役立つほか、建築と造園の連携を深めたい設計者や学生に最適な一冊です。
建築とランドスケープ・造園を同時に考えたい人におすすめの一冊になります。
動いている庭
発売日:2015年2月26日 ページ数:336P
「動いている庭」は、フランスの造園家ジル・クレマンによる、庭と自然に対する革新的な思想と実践を綴った名著です。
クレマンは、自然を支配するのではなく、「できるだけあわせて、なるべく逆らわない」という姿勢で、植物や土地の動的なふるまいを尊重しながら庭をつくる哲学を打ち立てました。
この考えは、従来の整然と設計された庭園像を覆し、土地のもつ潜在的な力や植物の自律的な成長を受け入れる「生きている庭」「変化し続ける庭」という新しい造園概念を提案しています。
本書では、自邸「谷の庭」での実験や観察を通して、庭がどのようにして人間の想像を超えて進化し、美しさを育んでいくかが、豊富なカラー写真とともに描かれます。
自然と共にあることの驚き、喜び、そしてときに恐れさえも、庭を通じて再発見していく過程は、まさに思想と実践の融合であり、単なる造園書にとどまりません。
造園・建築・環境デザインに携わるすべての人にとっての必読書といえるでしょう。
自然と人が生活する場所の関係性について考えたい人におすすめの一冊になります。
建築と庭 西澤文隆「実測図」集
発売日:1997年6月1日
「建築と庭」は、建築家・西澤文隆が日本の古建築と庭園を丹念に実測し、42件の詳細な図面としてまとめた貴重な記録集です。
厳島神社や桂離宮、修学院離宮などの名建築と庭園が織りなす空間のつながりや素材感を、繊細な鉛筆のタッチで表現しており、日本の伝統的な建築文化の深さを実感できます。
庭と建築の関係性を多角的に捉えたユニークな分類や、内田祥哉や安藤忠雄ら著名建築家の解説も収録されているため、建築や造園に携わる人にとっては必見の資料であり、空間を理解し感じる力を養うための重要な一冊です。
日本の建築と庭について知りたい人におすすめの一冊になります。
日本建築
こちらは、日本建築について詳細に学びたい人におすすめの本・参考書になります。
建築デザインの解剖図鑑
発売日:2013年6月3日 ページ数:176P
「建築デザインの解剖図鑑」は、江戸時代から昭和までの日本のまちなみや建築デザインを、豊富な図解で読み解く一冊です。
坂道や橋、水路、路面電車、屋台、お地蔵さんなどの意匠や配置に込められた歴史や工夫をわかりやすく解説し、身近な風景の見方を一変させます。
本書では、地形やまちなみのルール、建築の細部に至るまで、伝統と暮らしの知恵がどうデザインに反映されてきたかを探求しています。
まち歩きの楽しみ方や調査のポイントも紹介されており、建築ファンはもちろん歴史や文化に興味がある人にもおすすめの一冊です。
歴史的背景と日常の景観を結びつけ、見慣れた街を新鮮な目で楽しめる内容となっています。
日本の建築デザインについて詳細に知りたい人におすすめの一冊になります。
日本の建築家解剖図鑑
発売日:2020年1月22日 ページ数:160P
「日本の建築家解剖図鑑」は、明治から昭和にかけて活躍した63人の日本人建築家とその代表作を、美しいイラストとわかりやすい文章で紹介する一冊です。
辰野金吾や伊東忠太、内藤多仲など明治期の巨匠から、村野藤吾や堀口捨己の大正期、丹下健三や芦原義信の昭和戦前期、そして大谷幸夫や黒川紀章ら戦後期の建築家まで幅広く解説しています。
彼らの建築思想や技術、社会背景を踏まえた名作を通じて、日本建築の歴史と魅力が深く理解できます。
現存する建物の見学も推奨されており、建築ファンや学びたい人に最適なガイドブックです。
また、外国人建築家の影響や大工技術、インテリアデザインのコラムも充実しており、多角的に日本建築を知ることができます。
日本建築家と日本建築について関係づけて学びたい人におすすめの一冊になります。
カラー版 図説 日本建築の歴史
発売日:2020年12月19日 ページ数:104P
日本建築の流れを体系的に、しかも視覚的に学びたい方に最適なのが『カラー版 図説 日本建築の歴史』です。
縄文時代の住居から近代の擬洋風建築まで、建築の変遷をコンパクトにまとめた一冊で、建築史の入門書としてはもちろん、資料集としても優秀な内容となっています。
本書の特長は、すべてのページが見開き完結型で構成されている点や、それぞれのテーマごとに「3つの要点」を整理して提示しており、初学者でも理解しやすく、どこから読んでもスムーズに学べる構成です。
カラー写真と豊富な図版により、建築様式の違いや空間構成が視覚的に伝わるよう工夫されており、文字だけでは把握しづらい日本建築の特徴を直感的に理解できます。
仏教建築、神社建築、書院造や茶室、さらには町家や民家といった民間建築に至るまで、幅広いジャンルを網羅しています。
建築系の学生や設計関係者だけでなく、歴史や文化に興味がある一般の読者にもおすすめの一冊です。
建築における「日本的なもの」
発売日:2003年4月25日 ページ数:332P
「建築における「日本的なもの」」は、著名な建築家・磯崎新が日本建築の本質を再考察した一冊です。
本書では建築が国家の欲望の象徴なのか、それとも時代を変える革命の兆しなのかという問いを起点に、西洋のモダニズム建築を独自に取り入れ変形させてきた日本近代建築の歴史を鮮やかに描き出します。
磯崎自身の建築活動を振り返りながら、伊勢神宮や重源、桂離宮といった伝統的な建築遺産から、現代における都市のあり方まで、多角的に日本建築の「日本的」な側面を探求しています。
内容は、日本的な空間の構成や趣味、構築と空間の関係性をはじめ、近代主義の視点からの桂離宮の解釈、重源という歴史的課題、そして伊勢神宮に象徴される日本建築の起源と持続性についての深い考察が展開されています。
建築を通じて日本文化や社会の根源に迫る、世界的な視野と鋭い洞察に満ちた建築論の決定版ともいえる作品であり、日本建築の本質を理解したい人におすすめの一冊になります。
杉本博司が案内する おさらい日本の名建築
発売日:2020年9月7日 ページ数:200P
「杉本博司が案内する おさらい日本の名建築」は、現代美術家・杉本博司が選び、独自の視点で紹介する日本の名建築50選を収めた1冊です。
日本の伝統建築がモダニズム建築に与えた影響や、世界的に評価される日本の現代建築家たちの功績を背景に、日本人が改めて自国の建築の魅力を再認識できる内容になっています。
建築の歴史と美学、技術と精神性を横断的に学べる一冊で、日本建築の奥深さを味わいたい人におすすめの一冊になります。
見立ての手法 : 日本的空間の読解
発売日:1990年8月10日 ページ数:330P
「見立ての手法 : 日本的空間の読解」は、国際的に活躍する建築家・磯崎新によるユニークな建築論集です。
本書では、「間」や「桂」「庭」「舞台空間」といった日本的空間の特徴を深く掘り下げています。
伝統と現代、形式と空間の関係性を読み解きつつ、現代日本の建築や都市の状況、ポストモダン以降の展望まで幅広く論じられており、日本文化の独自性を建築的視点で考察する貴重な一冊となっています。
日本の近代建築
発売日:1993年10月20日 ページ数:267P
発売日:1993年11月22日 ページ数:285P
「日本の近代建築」は、日本における西洋建築の受容と展開を辿る一冊です。
ヴェランダコロニアルや下見板張りの西洋館から始まり、御雇建築家による本格的な建築、日本人建築家の誕生、そしてアール・ヌーヴォーやモダニズムの波まで、建築家の思想や時代背景とともに明快に描かれています。
上巻では幕末から明治期にかけての建築導入期を扱い、下巻では大正から昭和期における「建築とは何か」を模索した第二・第三世代の内省と挑戦が展開されます。
洋風建築の輸入から独自の近代建築への昇華までを、文明・技術・社会との関係性を交えて考察した本書は、日本建築の歩みを深く理解したい人におすすめの一冊になります。
ファスト化する日本建築
発売日:2025年4月24日 ページ数:304P
「ファスト化する日本建築」は、森山高至氏が近年の日本建築に蔓延する「早い・安い・簡単」という「ファスト志向」がもたらす弊害を鋭く批評する一冊です。
公共施設、住宅、商業施設、都市、さらには国家レベルの建築まで、あらゆる場面で進行するファスト化や見た目優先のデザイン、安価な建材、理念なき大型プロジェクトの結果、急速な劣化や文化の喪失が社会全体に波及しつつある現状を、豊富な事例とともに告発しています。
本書では、歴史的背景や建築文化の本質をひもときながら、なぜ本物の素材や職人が姿を消し、空間の質が損なわれていくのかを徹底解説しています。
そして、建築をめぐる人材、制度、都市政策にまで切り込み、持続可能な建築とは何かを問います。
建築に関わる人だけでなく、私たちの暮らしや社会のあり方に疑問を感じているすべての人に読んでほしい一冊になります。
世界・西洋建築
こちらは、世界や西洋の建築について詳細に学びたい人におすすめの本・参考書になります。
カラー版 図説 建築の歴史: 西洋・日本・近代
発売日:2013年12月15日 ページ数:184P
「カラー版 図説 建築の歴史: 西洋・日本・近代」は、建築史を一望したい人にとって理想の一冊です。
本書は、西洋・日本・近代の建築史を横断的に学べる点で他に類を見ない構成をもち、建築の「様式」や「空間構成」を視覚的に理解できるよう、鮮やかなカラー写真と精緻なイラストを豊富に掲載しています。
各トピックは、見開きの2ページで1テーマを完結させる構成になっており、歴史的な流れを追いつつも、興味のある部分だけを拾い読みすることもできます。
さらに、「写真では伝わりにくい」構造や詳細に関しては、イラストによって建築空間のリアリティを再現しています。
視覚的な理解が重視されているため、初心者にも親しみやすく、専門的知識がなくても建築の魅力に触れることができます。
本書の特筆すべき点は、西洋と日本、そして近代建築を一冊で俯瞰できる構成で、分断されがちな地域や時代の違いを超え、建築史全体を通史的にとらえたい方には最適です。
各時代の代表的な建築を取り上げており、旅行や美術館巡りをより深く楽しむための教養書としても活用できます。
建築の多様な姿とその背景を、体系的に学びたい人におすすめの一冊になります。
カラー版 図説 西洋建築の歴史
発売日:2021年12月30日 ページ数:120P
「カラー版 図説 西洋建築の歴史」は、ヨーロッパ建築の全体像を、体系的かつビジュアルに学べる一冊です。
古代ギリシアから中世ゴシック、そして近世ルネサンスやバロックに至るまで、西洋建築の核心を時代様式ごとに丁寧に解説した一冊であり、建築だけでなく美術・歴史に関心のある読者にもおすすめです。
本書は「古代」「中世」「近世」の三部構成で、各章の冒頭にその時代様式の概説があり、続く見開きページでは「3つの要点」で内容を簡潔に整理されており、紙面は視覚的にもわかりやすく、建築の流れを頭に入れやすい構成になっている点が最大の特徴です。
ドーリア式やイオニア式といった古代ギリシアの建築美、コロッセウムやバシリカに見るローマの実用性と壮麗さ、ゴシック大聖堂における神の光の象徴、さらにはルネサンス建築の古典的秩序やバロック建築の劇的な造形表現まで、それぞれの建築が生まれた背景と美意識を深く理解できる内容となっています。
また、巻末には「学習課題」も用意されており、建築史の授業・自主学習にもしっかり対応しています。
建築を学ぶ学生だけでなく、旅行や芸術鑑賞が好きな方にとっても、ヨーロッパの街並みや歴史的建築をより深く楽しむためのガイドブック的存在になります。
本格的な西洋建築史を、視覚的にわかりやすく、かつ体系的に理解したい人におすすめの一冊になります。
西洋の名建築 解剖図鑑
発売日:2023年3月26日 ページ数:176P
「西洋の名建築 解剖図鑑」は、古代から近代までの4000年にわたる西洋建築の歴史を、厳選された70の名建築を通して学べる画期的な入門書です。
パルテノン神殿やパンテオン、アルハンブラ宮殿、ヴェルサイユ宮殿、サヴォア邸など、多様な建築物を豊かなイラストと詳細な解説で紐解き、なぜそれらが「名建築」と称されるのか、その背景にある社会・文化・技術・思想をわかりやすく伝えます。
建築様式の境界に囚われず、実際の建物同士の影響や土地柄、時代ごとの特徴を俯瞰しながら理解を深められるため、西洋建築史の既存の知識を持つ人にも新たな発見がある内容です。
建築の基礎用語や様式ごとの特徴も丁寧に解説されており、初学者から専門家まで幅広く対応しています。
ヨーロッパ旅行の際のガイドとしても最適で、建築を通じて歴史と文化の奥深さを体感できます。
西洋建築の美と価値を、ビジュアルと知識の両面から楽しみたい人におすすめの一冊になります。
コンペ・ポートフォリオ・プレゼン
デザイン・クリエイティブ業界を目指す人のための ポートフォリオ見本帳
発売日:2019年2月1日 ページ数:130P
「ポートフォリオ見本帳」は、採用に直結したリアルな実例32点を分析しながら、成功するポートフォリオ制作の全体像を教えてくれる一冊です。
本書の魅力は、単なるレイアウトの紹介にとどまらず、各業界別に分けて、「企業が求める視点」から見た解説が加えられている点で、自分の目指す分野に最適化された見せ方やアピールポイントが明確になります。
さらに、制作のワークフローやスケジュール、就活の基本知識、さらには造本や印刷方法など実務的な情報も網羅しているため、「何から始めればいいのか分からない」という初学者にも安心です。
とくに注目すべきは、実際に内定を勝ち取ったポートフォリオを掲載している点です。
成功した事例を見ることで、自分の作品に足りない視点や構成の工夫が見えてきます。
これからポートフォリオを作る人にも、すでに制作を始めている人にもおすすめの1冊になります。
分析 建築コンペ・プロポーザル: 要項・提案・グラフィックを読み解く
発売日:2025年4月26日 ページ数:160P
「分析 建築コンペ・プロポーザル: 要項・提案・グラフィックを読み解く」は、建築コンペ・プロポーザルから厳選された10事例をもとに、プレゼンテーションやグラフィックの基本事項から、どのようにしてプレゼンテーションが選定されるのか、最優秀案に選ばれる提案の特徴を明らかにしています。
建築設計における発注者と設計者のコミュニケーションを軸に、なぜ特定の提案が選ばれたのかを解きほぐし、コンペ要項のデザインやプレゼンボードの評価ポイント、市民との関係づくり、戦略的なグラフィック表現など多角的な視点で読み解く解説を収録しています。
さらに審査プロセスや公開性が設計の質に与える影響をテーマにしたインタビューも掲載されており、コンペを理解し質の高い設計提案を行うための貴重な知見を提供する内容となっています。
コンペの仕組みから考えたい人におすすめの一冊になります。
みんなの建築コンペ論 建築・都市レビュー叢書
発売日:2020年7月22日
「みんなの建築コンペ論」は、建築家と建築史家の視点から、建築コンペの意義と課題を問い直す一冊です。
新国立競技場コンペの混乱を起点に、建築コンペは本当に社会に価値をもたらしているのかという根源的な疑問に迫ります。
歴史をさかのぼりつつ、日本におけるコンペの制度や発注方式の変遷を明らかにし、建築と社会との乖離、コミュニケーション不全の本質を浮き彫りにします。
本書は、良い建築とは何かや、どう決めるのかといった問いを共有しながら、今後の建築コンペが目指すべき新たなモデルを提案し、公共性や合意形成のプロセスに重点を置いた、より開かれたコンペのあり方を模索しています。
建築に関わる人だけでなく、公共空間や社会の意思決定に関心のあるすべての人におすすめの一冊になります。
初めて学ぶ建築コンペ・卒業設計
発売日:2008年11月20日 ページ数:95P
「初めて学ぶ建築コンペ・卒業設計」は、建築設計のアイデアコンペや卒業設計を始めて経験する人のための実践的な入門書です。
豊富な実例と図版を通じて、初心者でも迷わず設計を進められるようサポートしてくれます。
はじめての設計課題に挑む学生や、設計コンペに興味を持ち始めた人にとっておすすめの一冊になります。
建築家が教える人生を変える驚異のプレゼン
発売日:2012年2月28日 ページ数:191P
「建築家が教える 人生を変える驚異のプレゼン」は、プレゼン力を磨きたい建築家・学生に向けて、第一線で活躍する20人の建築家・デザイナーがその極意を語る一冊です。
単純なプレゼンの技法や考え方だけでなく、建築プレゼンにおける「哲学」を学ぶことができ、プレゼンの根本を知ることにもつながります。
また、実際のプレゼンシートや模型などの実例も豊富に掲載され、言葉・図面・空間の説得力を高める内容が満載です。
建築を伝えるために必要な「考え方」と「哲学」を学べる、プレゼンに悩む人におすすめの一冊になります。
図解 建築プレゼンのグラフィックデザイン
発売日:2015年12月10日 ページ数:83P
「図解 建築プレゼンのグラフィックデザイン」は、建築設計におけるプレゼンテーションシートの「見せ方」に特化した初の本格的なガイド本です。
本書では、勝てるプレゼンを実現するためのビジュアルデザインの基本と応用を、豊富な実例と共に図解で丁寧に解説しています。
理論編では視覚的ヒエラルキーや感覚的アプローチの違いを分析し、実践編では実際の入選案を通して「読みやすく、伝わる」資料の作り方を明かしています。
設計にグラフィックの力を活かしたい人におすすめの一冊になります。
建築プレゼンの掟
発売日:2008年6月1日 ページ数:188P
「建築プレゼンの掟」は、隈研吾や中村拓志、平田晃久といった第一線で活躍する建築家たちが、それぞれのプレゼンテーションの手法を語ることで、建築におけるプレゼンの本質を掘り下げる一冊です。
プレゼンは単なる説明ではなく、相手との重要なコミュニケーションの場であり、自身の思想や空間への考えをいかに伝えるかが問われます。
本書では、言葉の選び方や模型の見せ方、相手の心に届くストーリーの組み立て方、アイデアを一枚の図に込める技術などが、各建築家の具体的なエピソードを通して紹介され、プレゼンによって建築の価値が左右されるという現実がリアルに浮かび上がります。
自らの考えを的確に伝え、他者と共有し、合意を形成するために何が必要かを問いかける本書は、建築を学ぶ学生や実務者にとって、プレゼンという行為を根本から見直す契機を与えてくれる内容となっています。
建築のプレゼンの意味を、1つ1つ理解したい人におすすめの一冊になります。
構造
こちらは、構造について学びたい人におすすめの本・参考書になります。
改訂版 図説 やさしい構造力学
発売日:2017年9月14日 ページ数:204P
構造力学に苦手意識がある人や、もう一度基礎から学び直したい人に向けた入門書「改訂版 図説 やさしい構造力学」は、手描きのイラストによる丁寧な図解と、誰でも理解できるよう工夫された解説が魅力の一冊です。
数学や物理が得意でなくても、解法に従って進めるだけで、自然と理解できるように構成されています。
内容は力の基礎や釣り合い、反力、トラス、応力度、たわみ、不静定構造など、建築に必要な構造力学の基本を幅広くカバーしています。
構造を学び始めたばかりの建築学生はもちろん、資格試験の学習にも最適で、構造力学への苦手意識を払拭し、自信を持って学びを進めたい人におすすめの一冊になります。
図解でよく分かる建築構造入門
発売日:2023年1月27日
「図解でよく分かる建築構造入門」は、建築構造の基本をしっかり理解したい人に向けて、視覚的にわかりやすく解説された一冊です。
力といった初歩の概念から、応力の計算方法、構造別の断面算定、木造、鉄骨造、RC造など、幅広いテーマを多くの図解や例題を交えて丁寧に解説しています。
乃村工藝社など大手企業でも研修用テキストとして採用されている実績があり、専門書としての信頼性も高いのが特徴です。
また、インテリアデザインに関する知識や図面、パース表現まで扱うため、単なる構造の入門書にとどまらず、インテリア設計全般の基礎力を養いたい方にも適しています。
実務に活かせる本格的な知識を身につけたいと考える人におすすめの一冊になります。
世界で一番おもしろい 構造デザイン
発売日:2024年12月3日 ページ数:192P
「世界で一番おもしろい構造デザイン」は、建築設計の可能性を広げる構造設計の役割と面白さを、第一線で活躍する日建設計の構造エンジニアたちが実例を通して伝える入門書兼実践ガイドです。
構造設計というと、安全や耐震といった「守り」の要素が注目されがちですが、本書ではその枠を超えて、創造的な空間づくりにおける構造の「攻め」の視点に光を当てます。
ZHA案の新国立競技場やホキ美術館、新宿住友ビルの大改修など、著名プロジェクトを多数取り上げながら、「構造が建築のかたちを導く」プロセスを豊富なスケッチや図版とともに紹介しています。
さらに、素材・解析・表現・安心という4つの技術領域に関するQ&Aや、構造設計のキャリア・歴史についての付録も充実。木造から鉄骨造、BIMやデジタルツールまで、現代建築に求められる知識を体系的に学べます。
建築を学ぶ学生や構造設計に関心のある方はもちろん、意匠設計や実務に携わる人にとっても、新たな視点と発想のヒントを得られる一冊です。
構造を面白く、かつ新しい視点から学びたい人におすすめの一冊になります。
建築基準法・法規
こちらは、建築基準法・法規について学びたい人におすすめの本・参考書になります。
史上最強図解 よくわかる建築基準法
発売日:2009年11月20日 ページ数:336P
「史上最強図解 よくわかる建築基準法」は、建築基準法を誰にでも理解しやすい平易な文章と豊富なイラストや図解でわかりやすく解説した入門書です。
建築基準法を初めて学ぶ人でも全体の概要がつかめ、次の学習ステップにつなげられる内容となっています。
本書は全8章構成で、基本用語や面積・高さの計算方法、建築手続き、室内環境、構造強度、防火・避難規定、都市計画や街づくりに関するルールまで、建築基準法の主要なポイントを体系的にカバーしています。
これにより、実務者はもちろん、学生や建築に関わるすべての人に役立つ一冊になります。
いちばんやさしい 建築基準法 改訂3版
発売日:2025年6月5日 ページ数:256P
「いちばんやさしい 建築基準法 改訂3版」は、難解になりがちな建築基準法を、読みやすい文章とイラスト図解でわかりやすく解説した入門書です。
建築士を目指す人や建築業界の関係者、また家づくりを考える一般の方にもおすすめで、この一冊があれば建築基準法の基本から改正点までスムーズに理解できます。
章立ても目的別にわかりやすく構成されており、火災や災害からの安全確保、快適な住環境づくり、法の遵守まで幅広くカバーしている一冊になります。
身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規
発売日:2025年8月2日 ページ数:220P
「身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規」は、SNSや書籍で人気の建築基準法ブロガー・そぞろ氏が、日常で見かける建物や有名建築、事件など40の事例を通じて、建築法規をマニアックに、でも楽しく解説する一冊です。
「テーマパークの茅葺屋根は防火規制にどう適合?」「階段を外に設置するのはなぜ?」「なぜスカイツリーの高さは634mじゃない?」など、誰もが一度は疑問に思ったことのある建物の謎を、法規の観点から解き明かします。
防火・避難・斜線制限・採光・確認申請などの基本テーマが章立てされており、イラストやコラムも豊富で、読んで学べる実用書に仕上がっています。
現場経験豊富な著者が、複雑で敬遠されがちな建築法規を「わかりやすく」「面白く」変換して解説しています。
設計者や学生はもちろん、法規を事例を通して学びたい人におすすめの一冊になります。
卒業前後におすすめの本
こちらは、卒業前後や就職したばかりの人におすすめの本・参考書になります。
新米建築士の教科書
発売日:2017年3月21日 ページ数:271P
「新米建築士の教科書」は、建築士になるためではなく、「建築士として食っていく」方法を身につけるための実践的な指南書です。
日々の業務で役立つチェックリストやToDoリストも豊富で、新人教育の教本としてだけでなく、経営者やベテランの指導用としても活用可能です。
誰にでもできる簡単な習慣から始まり、実際の仕事で使える細かく具体的なアドバイスが網羅されています。
大学で教わる理論や資格取得のための知識とは違い、実務で即戦力となる具体的なスキルとノウハウが得られる点が特徴で、一流の現場でないとなかなか身につかない「現場感覚」や「スタッフ仕事」の全体像を学べる一冊になります。
建築士になる前もなってからも必ず役立つ! 建築士1年生が読む本
発売日:2023年3月14日 ページ数:279P
「建築士になる前もなってからも必ず役立つ!建築士1年生が読む本」は、建築士を目指す人やなりたての人に向けた、実務に直結する入門書です。
設計から工事監理、計画の提案、住宅の維持管理、プロの抑え処まで、建築士の仕事を8つのステップに分けて丁寧に解説しています。
契約や法令対応、図面の描き方、現場対応まで、流れに沿って学べる構成になっています。
著者の経験に裏打ちされた言葉が、建築士のリアルをやさしく、誠実に伝えてくれます。これから建築士としてスタートする人におすすめの一冊になります。
今回は以上になります。

![建築学生におすすめの本・参考書一覧[ジャンルや種類別に紹介]](https://iarchway.com/wp-content/uploads/2025/07/eyecatch-5.jpg)












































































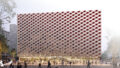




Comment